企業の経費削減とは、会社の収益を高める、または赤字を防ぐことを目的に、不要または過剰な支出を抑える取り組みのことです。
利益率を改善したり資金繰りを安定させたりするために、多くの企業で継続的に行われていて、昨今の物価高騰に伴い、経費削減・コスト削減の取り組みを強化している会社も多くなってきています。
本記事では、一般的な企業での経費削減・コスト削減の進め方から、実施する際の注意点をご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。
目次
経費削減の主な対象

会社の経費を大きく分類すると、オフィスコスト・オペレーションコスト・エネルギーコストの3つになります。
| オフィスコスト | 賃料、通信費、消耗品費、備品費など |
| オペレーションコスト | 人件費、物流費、外注費など |
| エネルギーコスト | 電気代、ガス代、水道代などの水道光熱費 |
これらはさらに細分化され、例えばオフィスコストは賃料・通信費・消耗品費・備品費など、オペレーションコストは人件費・物流費・外注費など、エネルギーコストは電気代・ガス代・水道代などが挙げられます。これらのコストを削減することで、企業の利益率向上に繋げることができます。
細分化した経費の中で、経費削減・コスト削減の対象になりやすいものが以下になります。
| 人件費 | AI導入、残業の削減、パート・業務委託の活用 |
| 通信費 | 格安プランへの切替、電話回線の統合 |
| 水道光熱費 | 節水機器導入、LED電気機器導入、空調の適正化 |
| オフィス関連 | ペーパーレス化、サブスクリプションの見直し |
| 外注費 | 内製化の検討、業者の競争入札 |
| 交際費・出張費 | Web会議の活用、出張基準の見直し、接待の頻度 |
上記は一般的な企業の実例になり、業態や職種、会社規模によって様々な対象があります。
ここまで多くの対象があると、気になったものにすべて手を付けてしまいそうになりますが、手当たり次第実施すると、効果が限定的で長期的に見て悪影響を及ぼす可能性があるため避けるべきです。
経費削減は、まず固定費と変動費を区別し、固定費から優先的に見直すことが重要です。その際、次に紹介する注意点に気をつけながら施策を検討していく必要があります。
経費削減の注意点
経費削減を行う際には、単に「コストを下げる」ことだけに注目してしまうと、逆に企業の成長や信頼を損なう可能性があります。
以下は、経費削減を実施する際の主な注意点です。
短期的な効果だけを重視しない

大前提として、経費削減を行う際には「短期的な利益の追求」ではなく「長期的な視点での取り組み」が重要になります。短期的な削減策は即効性がある一方で、持続可能性に欠ける場合が多く、結果として企業の成長を妨げる要因となる危険性もあります。
例えば、従業員の給与や教育費、福利厚生を減らすことは、短期的なコスト削減の効果はありますが、社員の離職や生産性低下を招く危険性があり、長期的に見ると従業員のモチベーション低下や企業ブランドのイメージに悪影響を及ぼす可能性があります。
ですので、まずは企業のビジョンや戦略に沿った経費削減の施策を選ぶことが重要となります。その上で、運用工程の見直しや効率化を図ることで、無駄なコストを削減しつつ、業務の質を向上させられるでしょう。
ステークホルダーとのバランスや関係性を考慮する

前述の通り、従業員に過度な負担を強いる経費削減は、モチベーションの低下や離職率の上昇を招くこともありますが、内部だけではなく、顧客やエンドユーザといった外部にも影響することがあるため注意が必要です。
経費削減のために顧客サービスを低下させたり、商品やサービスの品質を落とすと、顧客満足度が低下し、顧客離れを招く可能性があります。
この状況に陥ってしまうケースの多くは、ステークホルダー全体への影響度を考慮せずに経費削減施策を実施していることが見受けられます。経営者・管理職の方は、施策を実施する前に現場の意見をヒアリングし、実施時の効果をシミュレーションし、それらを踏まえて各施策のメリット・デメリットを事前に把握した上で、施策の実施有無を判断する必要があります。
削減対象と効果を可視化する

現状かかっている経費は把握されていると思いますが、経費削減のKPI(重要業績評価指標)を設定していない企業も多く見受けられます。
具体的なKPIを設定することで削減目標に対する進捗を数値で確認し、効果的な対策を立てやすくなりますが、KPIを設定しない場合、進捗状況の把握が難しく、目標達成が遅れる可能性があります。
まずはKGI(最終目標)を掲げ、そのKGIを達成するために必要なKPIをツリー状に整理します。そうすると、目標達成までのプロセスを明確にでき、組織として目指す先や戦略・戦術の共通認識を持つことができます。
KPIがないと、以下のようなリスクが発生しやすくなります。
- 手段・手法の目的化
- 進捗状況の把握の困難
- 目標達成への意識が薄れる
- 見直しの基準が曖昧になる
- 経費削減の貢献要因が不明確
- 効果のない施策へのリソース投下
この状態が続くと、組織全体のモチベーションが低下していき、労働生産性低下や従業員離職などを招いてしまいます。
改善と投資の違いを認識する
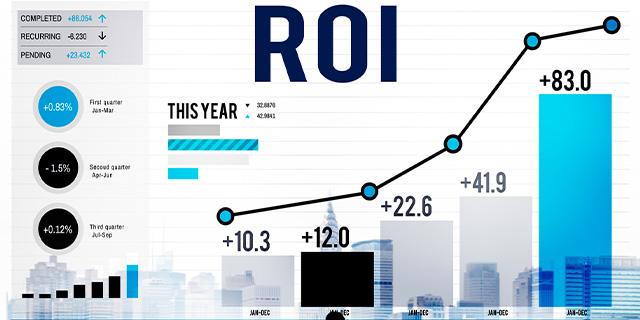
経費削減は、大きく分類すると以下の3つの方向性があります。
- 支出の抑制
固定費や外部委託費用などにかかる費用そのものを見直して削減する方法 - 費用対効果の最大化
経費を抑えつつ必要な部分に対しては投資することで、経費投入によって得られる効果の最大化を図る方法 - 戦略的な経費削減
各経費を単一的にコストカットせず、企業全体の経費を抜本的に見直して戦略的に削減する方法
この中で「支出の抑制」だけに集中してしまうと、目先の経費削減に囚われすぎて、企業の成長の妨げになってしまいます。企業や従業員の状況を見て、自社に適切な方法を選択して取り組んでいくようにしましょう。
動機形成を行った上で実施する

経費削減の施策に取り組む際、経費削減の目的を明確にし、その必要性を従業員に理解させることが不可欠です。
時代を問わず、変化を嫌う職場や従業員は数多く存在します。そんな環境で経営者・管理職から従業員へただ単に施策実施を依頼する形で行うと、従業員の「やらされている感」に拍車がかかり、施策のパフォーマンスも上がることなく消極的な姿勢に陥りやすく、施策の成果に関係なくモチベーション低下に繋がりやすくなってしまいます。
経費削減実現までのスピード感や効果を上げるには、従業員の当事者意識が大事です。経費削減の施策に対する動機形成こそが、KGI達成に向けての第一歩となります。
経営者・管理職の方は、従業員が抱えている現状維持バイアスを外せるためのきっかけを作り、変化の必要性やメリットを共有するための説明を怠らず、一方通行でないマネジメントを心がけるようにしてください。
具体的な経費削減の進め方
では、経費削減をどのように実施していけばよいでしょうか。ここからは、企業全体で同じベクトルを向いて経費削減へ継続的に取り組める進め方を説明していきます。
現状把握

経費は、家賃・人件費などの固定費と、原材料費・水道光熱費などの変動費に分類されます。まずは現状の固定費と変動費を把握し、見直しを図るべき経費があるどうか判断します。判断に困った場合、削減しやすい変動費から見直すのが効果的です。
次に、予実管理を行っている会社であれば、予算との比較を行います。予算と実際の支出を比較し、乖離が大きい項目や削減可能な項目を洗い出します。
予実管理や目標値がない会社は、日本政策金融公庫が公開している業種別の経営指標から、人件費や諸経費などの売上比率の実績値と照らし合わせて見ましょう。
日本政策金融公庫「小企業の経営指標調査」
https://www.jfc.go.jp/n/findings/shihyou_kekka_m_index.html
対象選定

現状把握をして予算や経営指標と実績値の乖離が浮かび上がってきたと思うので、あとは科目ごとに削減期待値と実現率を推測しつつ、実行しやすい科目の経費から優先順位をつけていきます。
経費削減のイメージができている会社であれば問題ないですが、判断に迷った場合、一般的に削減しやすい項目として挙げられる水道光熱費・通信費・消耗品費・交通費・旅費交通費・支払手数料・業務委託費などから対象にすると良いでしょう。
施策立案

対象となる科目が見えてきたら、今度は具体的な施策案を検討していきます。この時に大事なのは、可能性を狭めないために施策案をたくさん出してアイデアを拡散させることです。次に、拡散させた各施策ごとに削減効果(金額)と実行難易度(工数、期間)を評価します。
各施策の評価が終わったら、以下の基準に分類していきます。
- 【高効果・低難易度】短期間で大きな効果が期待できる施策
- 【高効果・高難易度】長期的な効果が見込めるが、実行に時間がかかる施策
- 【低効果・低難易度】小幅な削減効果が見込めるが、すぐに実行できる施策
- 【低効果・高難易度】あまり効果が見込めないが、実行に時間がかかる施策
1に該当する施策はなかなかないと思いますが、会社にとってメリットしかないので最優先で実施しましょう。次点は2と3に該当する施策で、イメージでは「2を進めていく合間に3を消化していく」スケジュール感で進められると良いでしょう。
4に該当する施策は、経費削減の観点からいうと会社にメリットを生み出すまでに時間を要しますし、効果のインパクトも高くありません。経費削減を視野に入れているということは、会社が安定している状態でない場合が多いでしょう。もし経営者や管理職の方が何となく4の施策を実施したいと思っていたとしても、削減効果と実行難易度の評価結果を見る限り、短〜中期での実施はあまりオススメできません。
協力体制構築

経費削減を成功させるには、会社全体での協力体制の構築が不可欠で、マネージャー層が率先して取り組む姿勢を見せることで、他の従業員のコスト削減に対する意識が高まり、前向きに取り組みやすくなります。
協力体制を構築するためには…
- 目的・意義・目標の共有
- 各自の役割と権限の明確化
- 進捗確認と軌道修正
といったことを、マネージャー層が中心となって行っていく必要があります。その際、従業員の負荷を軽減したり、部門間の連携を強化したりすると、より効果的な経費削減施策を実施することができます。
また、成果に応じた評価・インセンティブの付与などで、従業員のモチベーションを高める制度があると、より主体的に取り組む集団になっていくと思われます。
継続的な実施

企業の利益を確保し、事業を安定させるためには、経費削減の取り組みを継続させることが非常に重要です。
単発の施策であったり短期的なコスト削減に偏らず、業務効率化や生産性向上に繋がる施策を検討し、従業員のモチベーションを維持しながら、PDCAサイクルを回して継続的に改善していくことが重要です。
オススメの経費削減施策
以上が、経費削減に取り組む際に意識すべき進め方と注意点でしたが、具体的なイメージは浮かびましたでしょうか。
経費削減は目的ではなく手段であることを念頭に置き、無駄をなくす一方で、必要なコストは確保することが重要です。「具体的なイメージができない」「売上に影響するリスクが大きい」という場合は、無理に経費削減を推し進める必要はなく、手軽に始められる施策から着手すると良いでしょう。

本記事でオススメするのは水道光熱費の削減です。オフィス・店舗といった業態・施設に関係なく必ず発生する費用のため、削減が実現できれば長期的な効果が見込めます。
その中でオススメするのが、使用感・洗浄力を変えない新しい節水装置「ATOM -アトム-」です。
特許取得の独自構造で24段階も流量調整でき、節水率は最大80%超。水の勢いが強くなる先端装着タイプで、用途に合わせて好みの水量に調整でき、使用感を維持したまま水道代・ガス代・CO2を削減することができます。ほぼすべての水栓に対応していて、錆びにくく詰まりにくい仕様なので半永久的に使用できます。
また、消耗品費の経費削減でよく言われるのがペーパーレス化ですが、なかなか進まない会社も多いと思います。理由は様々ですが、電子化するための環境構築に要する初期導入コストに躊躇されているケースが多々見受けられます。
そんな場合は、ペーパーレス化の優先度を下げて、AO機器消耗品のコスト削減を行ってみるのも1つの手です。
トナーやインク、テプラなどの消耗品には純正品以外にも様々な種類が存在します。ずっと純正品を使用されている方は、これを機に純正品以外を使用してみてはいかがでしょうか。
この他にも経費削減のお役に立てる商材・サービスを多数取り扱っております。ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

